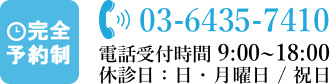新薬の研究開発、カギ握る企業の「攻めの姿勢」
科学記者の目 編集委員・安藤淳
2024年1月24日 2:00[会員限定記事]
韓国のソウル近郊、板橋(パンギョ)テクノバレーに、奇抜なデザインの巨大なバイオ医薬研究拠点がある。運営するのはCHAバイオメディカル・グループだ。世界の富裕層を相手に不妊治療を手掛ける病院など、複数の医療機関を傘下にもつ一方、再生医療などの研究に力を入れる。医師でもあるチャ・グァンヨル会長が一代で韓国屈指のバイオ医療集団に育て上げた。
ここで2023年10月、「未来の薬のための国際フォーラム」が開催された。会長が力を入れる再生医療や老化関連の研究、韓国の薬事規制の最新事情などの発表も面白かったが、それ以上に目を引いたのは学生参加者の多さだ。それもそのはず、同じ建物群のなかに約4000人が学ぶCHA大学の中核キャンパスがあり、医科学や生命工学の研究教育に力を入れている。企業が研究開発拠点に大学を併設する例は珍しい。

ソウル近郊で開いたCHAバイオメディカル・グループの国際フォーラムには学生らも多数参加した
韓国企業が始めた新たな産学交流
フォーラム参加者はCHA大学のほか米ハーバード大の幹細胞研究者や、慶応義塾大学の岡野栄之教授、世界初のiPS細胞を使った治療を実施した元理化学研究所の高橋政代ビジョンケア(神戸市)社長ら、そうそうたる顔ぶれ。医薬関連企業の参加者も多かった。第一線の研究者と学生、産業界の代表らが交流できる場を提供し、若手を育成する狙いがある。
チャ会長は産官学の壁をなくすことにより、「研究者や医療者が専門家としての役割を果たしながらビジネスも進められる環境を整えた」と強調する。まだ売り上げに貢献するような再生医療製品は出せておらず、投資リスクは無視できない。だが、攻めの姿勢を続ける。隣接地に細胞・遺伝子治療関連の研究・生産拠点となる新棟を約5億ドル(約740億円)を投じて建設する計画で、25年の完成を見込む。施設の1割程度を、国内外の研究機関などに貸し出す。

チャ・グァンヨル会長は研究開発に積極投資を続ける
バイオ医薬拠点が14年に完成してから、スタートアップが5社発足した。患者本人の幹細胞からオルガノイド(ミニ臓器)を作って治療に利用する再生医療をめざすオルガノイド・サイエンシズはその一例だ。重い腸疾患の患者を対象とする臨床試験に23年に着手した。他人の体内でも拒絶反応を起こしにくいiPS細胞を使った治療も3年内に始める計画だ。
「ベンチャー投資家らのオルガノイドに対する関心は高く、資金集めには困らない」(ユー・ジョンマン最高経営責任者)。当初は国の支援も得たが、研究が軌道にのるのに伴いベンチャーキャピタル(VC)などから約55億円を調達した。時間をかけて新しい治療法の芽を育て、ビジネスが立ち上がるまで伴走するというCHAのやり方は実を結びつつある。
日本はブレークスルー実現しにくく
日本のバイオ医薬産業育成は、やや手法が異なる。国がめぼしい分野に大きな予算をつけて産学協同の創薬プロジェクトを始動させ、「大御所」と呼ばれる研究者や著名な専門家をプログラムオフィサーにあてるのが日本流だ。スタートアップの立ち上げやVC投資獲得までの取り組みも、マッチング事業などを通して国の橋渡しを求める声が多い。
大手企業はこうして国のお墨付きを得たスタートアップに近づき、研究開発協力や特許のライセンス交渉に動く。これだと、どうしてもそこそこの成果が見込めそうな分野ばかりが取り上げられ、「水面下」の研究に光が当たらない。従来の延長線上にある成果は生まれても、真のブレークスルーは実現しにくい。
日本のバイオ医薬産業にも詳しいある米大手製薬企業の幹部は「企業はスタートアップが育つのを待つよりも、自ら大学などに入り込んで研究者自身も気づいていないような事業化への道へ導くべきではないか」と指摘する。国の政策は重要だが、それだけでなく企業がもう少しリスクをとって動くべきだという。
少しずつ動き出した新しい試み
日本でも新しい試みは少しずつ始まりだしている。住友ファーマはメンタルヘルス分野を中心に、外部の研究機関・企業と研究開発の比較的初期の段階から組み、デジタル技術を応用した診断・治療法の実用化をめざす「フロンティア事業」を展開する。
たとえば慶応義塾大医学部の精神疾患研究に早くから注目し、医師の主観に頼りがちで客観的に症状をつかむのが難しい、うつ病の診断研究で協力してきた。慶大発スタートアップで同大の岸本泰士郎特任教授が代表を務めるi2medical(川崎市)と組み、リストバンド型ツールを装着し、うつ病を数値やグラフで客観的に評価できるシステムの製品化を進めている。
慶大による研究成果の特許出願直後から、事業化へ向けて住友ファーマが伴走してきた。肝となるうつ病検出・重症度評価支援プログラムが23年3月、厚生労働省による初のプログラム医療機器の優先審査対象品目に指定された。住友ファーマのフロンティア事業では、米社との協力を含め、9件のプロジェクトがある。
時代の転換点こそ挑戦の機会
今後は人工知能(AI)などを駆使することで、新薬開発のプロセスや方法が大きく変わる可能性がある。開発の効率向上や低コスト化も期待できるが、残念ながら米欧の大手製薬企業やバイオベンチャー企業が大きく先行する。
日本ではスイスの製薬大手ロシュの傘下にある中外製薬が、日本IBMから移った志済聡子上席執行役員(デジタルトランスフォーメーションユニット長)のもと、デジタル技術を研究開発や事業のあらゆる分野で貪欲に取り入れている。しかしこれは例外に近い。多くの国内製薬企業は海外の動向を「様子見」しつつ、恐る恐る新しいやり方を試し始めた段階だ。

中外製薬はデジタル技術の導入を加速する(2023年11月、中外イノベーション・デーで戦略を説明する志済上席執行役員)
日本企業から生まれた医薬品が、世界の医薬品市場で占める比率は長く低下傾向にある。国内市場は縮小し、海外からの研究開発投資も減った。新たな技術が次々に登場し、時代の転換点にある今こそ、未知の部分が多くリスクを伴う研究開発にも挑戦する意味がある。このタイミングを逃せば、米欧との差はますます開くだろう。